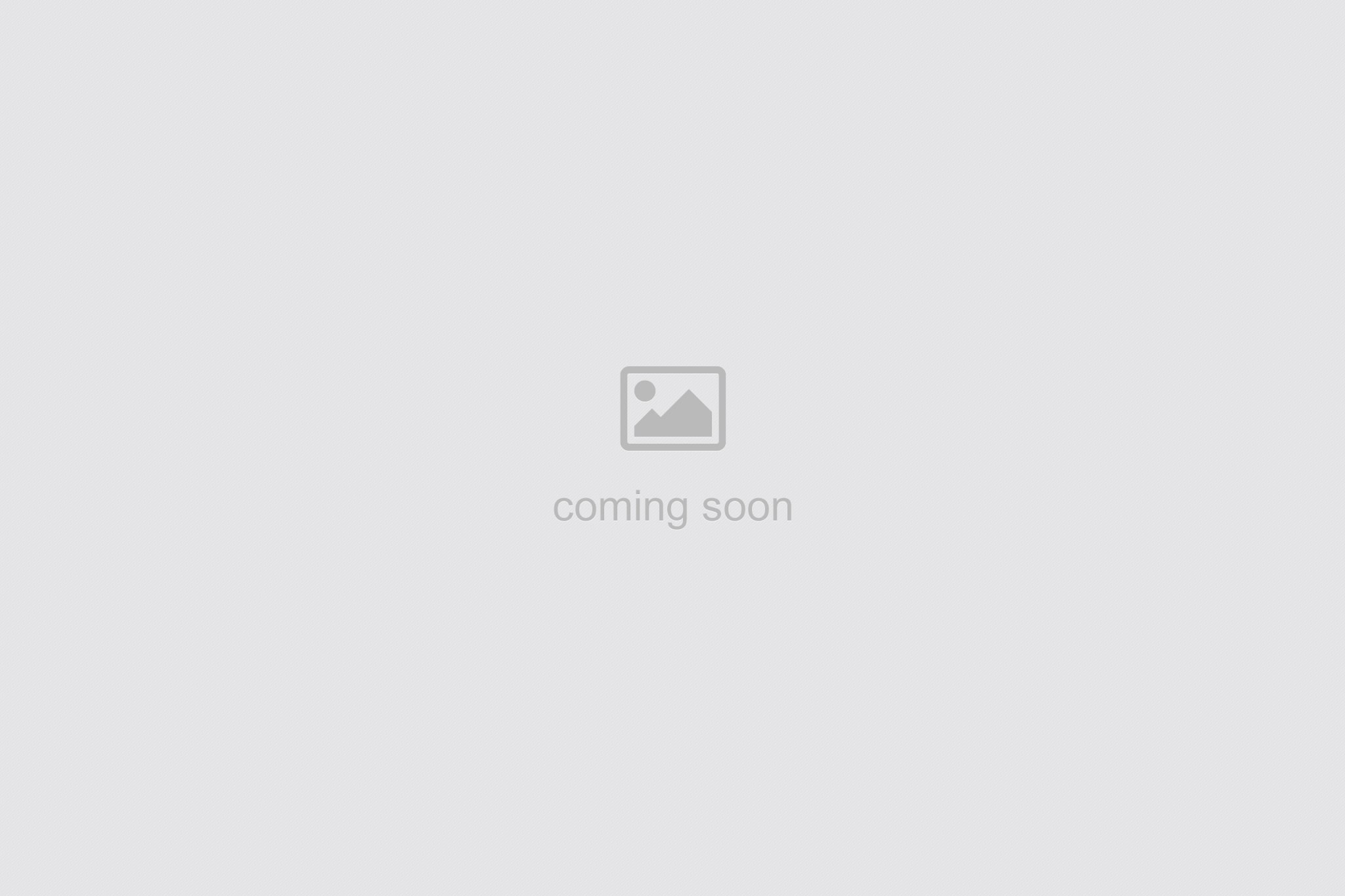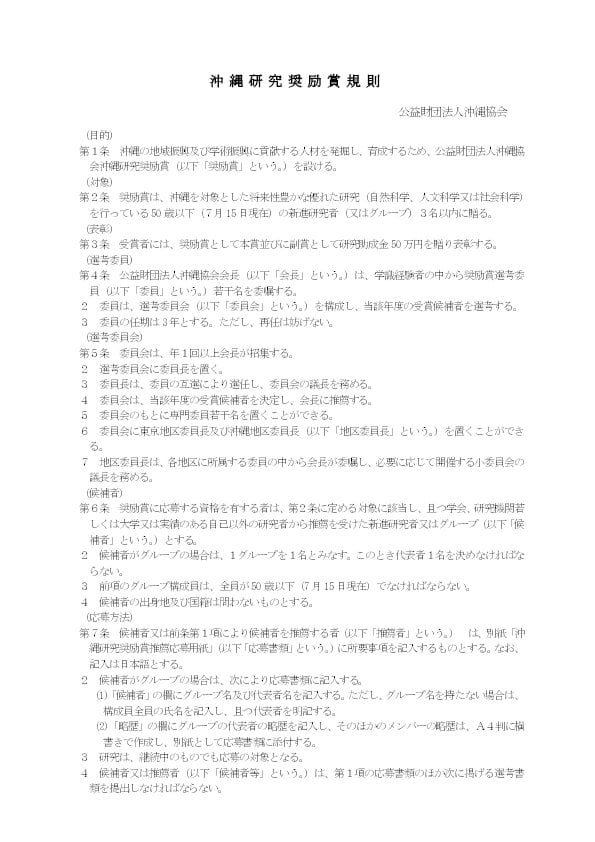沖縄研究奨励賞
沖縄研究奨励賞について
《沖縄研究奨励賞の設置》
沖縄研究奨励賞(奨励賞)は、当協会の設立目的にある「沖縄の振興施策への積極的な協力」に関連し、これを推進する事業として、沖縄の地域振興に貢献する人材を発掘し育成することを目指して、昭和54年7月に設置されました。
沖縄研究奨励賞(奨励賞)は、当協会の設立目的にある「沖縄の振興施策への積極的な協力」に関連し、これを推進する事業として、沖縄の地域振興に貢献する人材を発掘し育成することを目指して、昭和54年7月に設置されました。
《沖縄研究奨励賞の概要》
沖縄を対象とした優れた研究を行っている50歳以下(応募の年の7月15日現在)の新進研究者(又はグループ)を受賞対象としています。 応募しようとする方(応募者)の出身地及び国籍は問いません。応募にあたっては推薦応募の形式をとっており、応募者は大学、学会または実績のある研究者などからの推薦を受けて応募しなければなりません。 学会等から推薦された応募者は、その年に開催される選考委員会に諮られ、受賞候補者が選考されます。 沖縄協会会長は、選考委員会から推薦された受賞候補者の中から当該年度の受賞3件以内を決定します。 受賞者には、奨励賞として本賞と副賞50万円を贈呈し表彰するというものです。
沖縄を対象とした優れた研究を行っている50歳以下(応募の年の7月15日現在)の新進研究者(又はグループ)を受賞対象としています。 応募しようとする方(応募者)の出身地及び国籍は問いません。応募にあたっては推薦応募の形式をとっており、応募者は大学、学会または実績のある研究者などからの推薦を受けて応募しなければなりません。 学会等から推薦された応募者は、その年に開催される選考委員会に諮られ、受賞候補者が選考されます。 沖縄協会会長は、選考委員会から推薦された受賞候補者の中から当該年度の受賞3件以内を決定します。 受賞者には、奨励賞として本賞と副賞50万円を贈呈し表彰するというものです。
《広がりをみせる沖縄研究》
奨励賞は、これまでに115件(106名・9グループ)の受賞者を数えています。受賞に至らなかった研究の中にも受賞に値する研究が数多く含まれており、毎年開催される選考委員会での選考作業は、常に難航を極めています。奨励賞は、沖縄という特定の地域の専門的な研究を授賞対象としているにもかかわらず、近年では沖縄という限られた地域を超えて、 国際的な広がりのある普遍性を備えた研究もみられるようになりました。 また、応募者には、日本で研究活動を行っている外国からの研究者も含まれるようになりました。 沖縄研究の深さ、そして沖縄研究にかかわる人材の豊富さを実感させられます。
奨励賞は、沖縄の学術文化、地域経済の発展の基盤となる素晴らしい研究者とその研究を顕彰し続けています。
奨励賞は、これまでに115件(106名・9グループ)の受賞者を数えています。受賞に至らなかった研究の中にも受賞に値する研究が数多く含まれており、毎年開催される選考委員会での選考作業は、常に難航を極めています。奨励賞は、沖縄という特定の地域の専門的な研究を授賞対象としているにもかかわらず、近年では沖縄という限られた地域を超えて、 国際的な広がりのある普遍性を備えた研究もみられるようになりました。 また、応募者には、日本で研究活動を行っている外国からの研究者も含まれるようになりました。 沖縄研究の深さ、そして沖縄研究にかかわる人材の豊富さを実感させられます。
奨励賞は、沖縄の学術文化、地域経済の発展の基盤となる素晴らしい研究者とその研究を顕彰し続けています。
《終わりにかえて》
奨励賞の第1回の受賞者・大城喜信氏は、平成4年に沖縄協会が発行した 『沖縄研究奨励賞のあゆみ』の中で次のように述べています。
奨励賞の第1回の受賞者・大城喜信氏は、平成4年に沖縄協会が発行した 『沖縄研究奨励賞のあゆみ』の中で次のように述べています。
|
「沖縄は、地理的、歴史的、文化的、産業的な観点から研究テーマも豊富にあり、解決すべき課題も多い。しかしながら、沖縄では一般に研究開発に対する社会的評価が低く、 新しい分野に挑戦する者に対しては比較的冷淡であり、社会的には形が見えるまでは資金的 あるいは精神的支援の水準が低い段階にあると私は考えている。したがって、公的・私的研究機関を問わず研究者には厳しい条件が多いので、これを乗り越えるために余分なエネルギーが要求され、能力を十分に発揮しにくい環境であるといえよう。このような沖縄社会の空白部分に大きな光を当てたのが沖縄研究奨励賞であり、多くの研究者に目標を与えている」
|
『第45回沖縄研究奨励賞』受賞者
【受賞理由】
◆自然科学部門:2件◆(敬称略)
アリモドキゾウムシ根絶研究グループ 日室千尋(代表)
琉球産経株式会社・研究員他
〔研究題目〕
不妊虫放飼法を用いたアリモドキゾウムシ根絶に関する研究
〔受賞理由〕
米国のエドワード・ニップリングによって発案された不妊虫放詞による根絶法は、農薬の多大な環境負荷の根本的対策として世界中で注目されたが、この方法は、予算はもとより、システム的にノウハウや改善点が積み上げられ社会化する必要があり、実用化に多くの難問を抱えている。
この壁を突破し、実用化を証明したのが1993年に完成した沖縄県のミバエ根絶事業であり、世界的にも類例のない歴史的壮挙である。そのお陰で、マンゴーは大きな産業となり、園芸分野の振興が着々と進んでいる。
ヤンバルクイナを守るために気の遠くなるような「マングースの罠の設置」による成果は、この成功例と無縁ではない。
ミバエ類の歴史的成果を踏まえ、本研究のカンショ(サツマイモ)のアリモドキゾウムシの根絶事業は必然的なものと言えるが、その成功はミバエ根絶に続く歴史的な壮挙であり、難防除害虫対策の確たる幕開けである。
歴史的に見ると、カンショ(サツマイモ)は、沖縄はもとより、全国の食糧危機に極めて重要な役割を果たしたが、健康食品やバイオ資源としての可能性は無限的であり、これから主役になる作物である。アリモドキゾウムシに加害されたサツマイモは、イポメアマロンという有害物質が生成されるため、殆ど無価値となる致命傷がある。
本研究は既に久米島において成功を修め、国際的にも高い評価を受けているが、再侵入対策や広域にわたる応用に課題が残されていた。今回の研究は、再侵入が容易な津堅島(うるま市)で行われ、実用化に耐える成果を実証しており、広域な地域での応用の可能性も見い出している。
従って、この独創的な研究は「沖縄発世界へ」となると同時に、カンショを中心にした新しい一次産業の振興に多大に貢献するものである。これまでの長期にわたる根気強い研究に改めて敬意を表したい。
この壁を突破し、実用化を証明したのが1993年に完成した沖縄県のミバエ根絶事業であり、世界的にも類例のない歴史的壮挙である。そのお陰で、マンゴーは大きな産業となり、園芸分野の振興が着々と進んでいる。
ヤンバルクイナを守るために気の遠くなるような「マングースの罠の設置」による成果は、この成功例と無縁ではない。
ミバエ類の歴史的成果を踏まえ、本研究のカンショ(サツマイモ)のアリモドキゾウムシの根絶事業は必然的なものと言えるが、その成功はミバエ根絶に続く歴史的な壮挙であり、難防除害虫対策の確たる幕開けである。
歴史的に見ると、カンショ(サツマイモ)は、沖縄はもとより、全国の食糧危機に極めて重要な役割を果たしたが、健康食品やバイオ資源としての可能性は無限的であり、これから主役になる作物である。アリモドキゾウムシに加害されたサツマイモは、イポメアマロンという有害物質が生成されるため、殆ど無価値となる致命傷がある。
本研究は既に久米島において成功を修め、国際的にも高い評価を受けているが、再侵入対策や広域にわたる応用に課題が残されていた。今回の研究は、再侵入が容易な津堅島(うるま市)で行われ、実用化に耐える成果を実証しており、広域な地域での応用の可能性も見い出している。
従って、この独創的な研究は「沖縄発世界へ」となると同時に、カンショを中心にした新しい一次産業の振興に多大に貢献するものである。これまでの長期にわたる根気強い研究に改めて敬意を表したい。
琉球大学農学部・准教授 陳 碧霞
〔研究題目〕
琉球列島における伝統集落景観とフクギ屋敷林老木分布に関する調査研究
〔受賞理由〕
沖縄の伝統的屋敷は、多くの場合、周囲をフクギ林によって囲まれている。この沖縄独特の屋敷景観がどのような理由から生まれたものなのか、なぜ屋敷林にフクギが使われるのか、海辺から内陸に渡って植栽される防風林と屋敷林との関係はどうなっているのか。これらについて、本研究では、沖縄の風水思想、 自然環境、植生学の総合的観点から考察を行っている。
まず、土地抱護の風水思想に基づいた重層的防風林が、島嶼沖縄の自然環境と相まって災害をもたらす台風や季節風に対応していることを科学的に論じている。すなわち、風水思想に基づく沖縄の抱護は、台風や季節風などの風の脅威から屋敷や集落、耕地を護ることに重点を置いており、風水の「風」に特化していると言える。このことから、中国の風水を「大陸型風水モデル」と位置づけ、沖縄独特の風水を「島嶼型風水モデル」として分類している。
次に、諸外国のフクギ植栽に関する豊富な調査研究から、偶然に流れ着いたフクギの種子が西表島のフクギ屋敷林の始まりであり、これが沖縄全土に広がったという有用な仮説を立てている。これに基づき、琉球列島のほぼ全域に見られるフクギ屋敷林が沖縄固有の文化的・景観的遺産であることを示唆している。
また、本部町備瀬集落での事例研究において、伝統的フクギ屋敷林に対する観光客の関心、評価に加えて保全意識も調査し、フクギ屋敷林が沖縄の重要な観光資源であることを改めて確認している。
さらに、琉球列島に現存するフクギ3万本余の樹高と幹の太さ等を測定し、集落ごとの老木データベースを作成している。これによって、沖縄のフクギの空間分布を可視化し、今後のフクギ屋敷の包括的保全に向けて役立てることができるようにした。
本研究は、琉球列島との比較で中国、台湾、香港、韓国まで調査範囲を広げており、東アジアにおける沖縄の位置づけ、集落研究に大きく寄与することが期待される。また、単に専門的な植生学上の価値だけでなく沖縄の観光、地域振興にも貢献するものであり、沖縄研究奨励賞に値する。
まず、土地抱護の風水思想に基づいた重層的防風林が、島嶼沖縄の自然環境と相まって災害をもたらす台風や季節風に対応していることを科学的に論じている。すなわち、風水思想に基づく沖縄の抱護は、台風や季節風などの風の脅威から屋敷や集落、耕地を護ることに重点を置いており、風水の「風」に特化していると言える。このことから、中国の風水を「大陸型風水モデル」と位置づけ、沖縄独特の風水を「島嶼型風水モデル」として分類している。
次に、諸外国のフクギ植栽に関する豊富な調査研究から、偶然に流れ着いたフクギの種子が西表島のフクギ屋敷林の始まりであり、これが沖縄全土に広がったという有用な仮説を立てている。これに基づき、琉球列島のほぼ全域に見られるフクギ屋敷林が沖縄固有の文化的・景観的遺産であることを示唆している。
また、本部町備瀬集落での事例研究において、伝統的フクギ屋敷林に対する観光客の関心、評価に加えて保全意識も調査し、フクギ屋敷林が沖縄の重要な観光資源であることを改めて確認している。
さらに、琉球列島に現存するフクギ3万本余の樹高と幹の太さ等を測定し、集落ごとの老木データベースを作成している。これによって、沖縄のフクギの空間分布を可視化し、今後のフクギ屋敷の包括的保全に向けて役立てることができるようにした。
本研究は、琉球列島との比較で中国、台湾、香港、韓国まで調査範囲を広げており、東アジアにおける沖縄の位置づけ、集落研究に大きく寄与することが期待される。また、単に専門的な植生学上の価値だけでなく沖縄の観光、地域振興にも貢献するものであり、沖縄研究奨励賞に値する。
◆人文科学部門:0件◆
◆社会科学部門:0件◆
沖縄研究奨励賞規則及び選考委員名簿(PDF)
|
選考委員
赤嶺 政信 (琉球大学名誉教授)
安 藤 由 美 (琉球大学名誉教授)
上 原 靜 (沖縄国際大学総合文化学部教授)
大 屋 祐 輔 (琉球大学副学長)
カストロ ホアンホセ (琉球大学工学部教授)
狩 俣 繁 久 (琉球大学名誉教授)
櫻 井 國 俊 (沖縄大学名誉教授)
田 名 真 之 (沖縄県立博物館・美術館前館長)
西 田 睦 (琉球大学学長)
波照間 永吉 (名桜大学大学院国際文化研究科国際地域文化専攻教授)
比 嘉 照 夫 (名桜大学付属国際EM技術センター長・琉球大学名誉教授)
譜久山 當則 (沖縄振興開発金融公庫前理事長)
牧 野 浩 隆 (元沖縄県副知事)
宮 城 隼 夫 (琉球大学名誉教授)